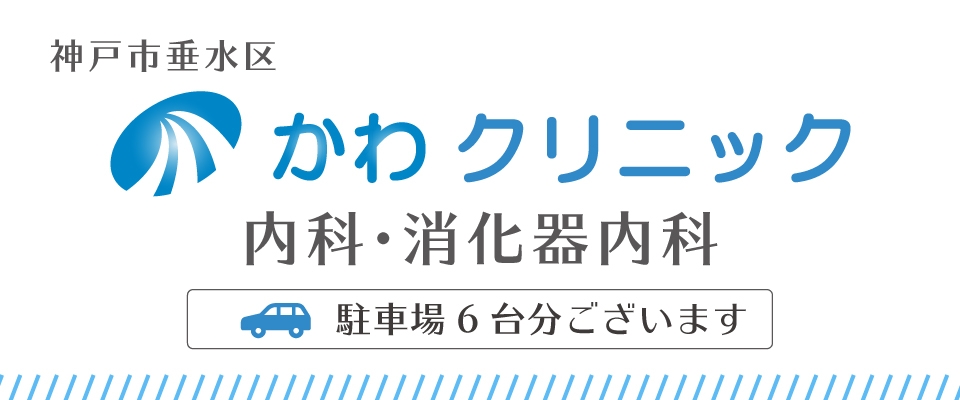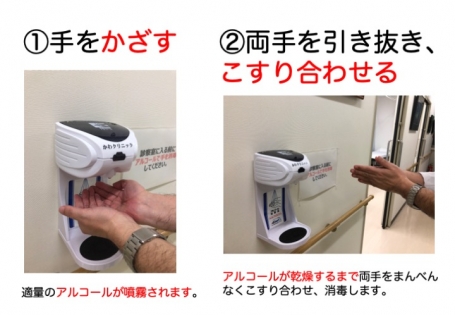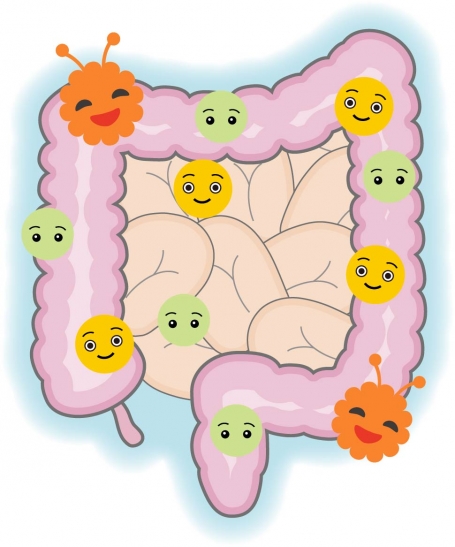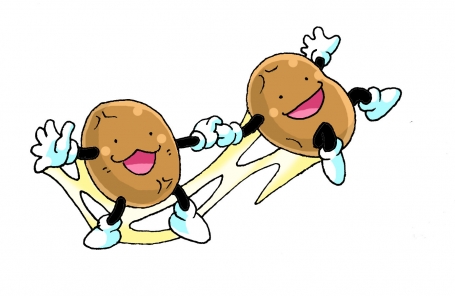今回の記事は、ピロリ菌除菌についてです。ピロリ菌は胃の粘膜に定着すると胃潰瘍・十二指腸潰瘍や胃がんなどを引き起こす細菌です。ピロリ菌の除菌を行うと、胃潰瘍・十二指腸潰瘍の再発抑制効果や、胃がん発生率の低下の効果が実証されています。ピロリ菌の除菌療法が世界中で行われており、日本でも保険適応となっています。
当院ではピロリ菌の診断治療を積極的に行っています。
ピロリ菌除菌療法の基礎知識
論文の内容に入る前に、除菌療法の基礎知識について触れておこうと思います。
除菌には胃酸分泌抑制剤と抗菌薬の併用療法が行われていますが、近年抗菌薬の一つのクラリスロマイシンに対して耐性を持つピロリ菌が出現し、除菌率の低下が問題になっています。
これまで胃酸分泌抑制剤としてプロトンポンプ阻害薬(PPI)を含む併用療法が広く使われていましたが、クラリスロマイシンに対する耐性菌により除菌率は70%程度に低下が問題になっていました。
2014年にPPIよりも強力な酸分泌抑制効果があるボノプラザン(カリウムイオン競合型アシッドブロッカー:P-CAB)が発売され、以後除菌療法に用いられています。このボノプラザンと抗菌薬アモキシシリン・クラリスロマイシンの3剤併用療法(VAC療法)では、クラリスロマイシン感受性菌だけでなく、クラリスロマイシンに耐性菌に対しても約90%の高い除菌率を示したことから、日本ではピロリ菌の一次除菌療法として広く行われています。
今回の記事では、日本人を対象に、ピロリ菌除菌療法のVAC療法のうち耐性菌の問題があるクラリスロマイシンを除いた、ボノプラザンとアモキシシリンの2剤併用療法(VA療法)の除菌効果を、VAC療法と比較検討した論文を紹介します。
論文の紹介
今回は、ピロリ菌の除菌療法についての論文でGutに掲載された"Seven-day vonoprazan and low-dose amoxicillin dual therapy as first-line Helicobacter pylori treatment: a multiplecentre randomised trial in Japan (ヘリコバクター・ピロリ一次除菌療法としての7日間のボノプラザンと低用量アモキシシリンによる2剤併用療法:日本での多施設での無作為比較試験)"を紹介します。
Seven-day vonoprazan and low-dose amoxicillin dual therapy as first-line Helicobacter pylori treatment: a multicentre randomised trial in Japan.
Suzuki S, Gotoda T, Kusano C, Ikehara H, Ichijima R, Ohyauchi M, Ito H, Kawamura M, Ogata Y, Ohtaka M, Nakahara M, Kawabe K.
Gut. 2020 Jan 8. pii: gutjnl-2019-319954. doi: 10.1136/gutjnl-2019-319954. [Epub ahead of print]
1.研究デザイン
【対象者】
2018年10月から2019年6月までの期間の日本の7施設で、腹部症状のある人や胃がん検診の目的で上部消化管内視鏡検査が行われた患者をエントリー。20歳から79歳までで胃の生検組織の培養からピロリ菌が検出された患者が対象。(ピロリ菌除菌歴を有する者・除菌療法の薬剤にアレルギーがある者・プロトンポンプ阻害薬の使用・抗菌薬やステロイドの使用がある者・妊娠や授乳中の者・同意が得られない者を除外)
【ピロリ菌同定と薬剤感受性試験】
2箇所以上の胃生検組織からピロリ菌を同定し、アモキシシリン・クラリスロマイシンの薬剤感受性試験を施行。
【研究アウトカム】
対象者を無作為に以下の2群に割り付ける
・VA2剤群(ボノプラザン20mg/回+アモキシシリン750mg/回を1日2回、7日間)
・VAC3剤群(ボノプラザン20mg/回+アモキシシリン750mg/回+クラリスロマイシン200mg/回を1日2回、7日間)
内服終了後少なくとも4週間後に尿素呼気試験で除菌判定を行う
2.結果
【除菌率】
(ITT解析)VA2剤群:84.5% VAC3剤群:89.2% P値:0.073
(PP解析)VA2剤群:87.1% VAC3剤群:90.2% P値:0.024
*対象となった全数を解析したITT解析では、VA2剤群のVAC3剤群に対する非劣勢は証明できなかった。
*対象からフィローアップできなかった症例や副作用で継続できなかった症例を除いた、PP解析ではVA2剤群はVAC3剤群に対して非劣性が証明された。
【クラリスロマイシン耐性がある条件での除菌率】
(PP解析)VA2剤群:92.3% VAC3剤群:76.2% P値:0.048
*クラリスロマイシン耐性がある群では、VA2剤群がVAC3剤群と比較して有意に除菌率が高かった。
【有害事象】
有害事象は下痢・腹部膨満感・便秘・皮疹などで両群に差は認めなかった。
3.結論
7日間のボノプラザンと低用量アモキシシリンの2剤併用療法は、ピロリ菌除菌療法として充分な除菌率を認めた。また、ボノプラザンを用いた3剤併用療法と比較してクラリスロマイシン耐性例に対して高い除菌率を認めた。有害事象は両群に差は認めなかった。
まとめ
近年、抗菌薬の使用拡大に伴い、抗菌薬が効かない細菌(耐性菌)が認められるようになり、治療に難渋するケースが増えてきており、問題となっています。なかでもクラリスロマイシン耐性菌は頻度が高く臨床上問題となっています。近年ピロリ菌の除菌療法は胃酸分泌抑制薬であるボノプラザンと、抗菌薬のアモキシシリンとクラリスロマイシンの3剤併用療法が広く行われており、日本では一次除菌療法として保険適応となっています。論文ではボノプラザンとアモキシシリンの2剤による除菌療法を、クラリスロマイシンを含んだ3剤の除菌療法と比較を行っています。
結果をまとめると以下のとおりです。
・2剤併用療法は3剤併用療法と同様の除菌効果がることは残念ながら示されなかったが、一次除菌療法としては充分に許容できる高い除菌率を認めた。
・クラリスロマイシン耐性例ではむしろ2剤併用療法のほうが3剤併用療法よりも有意に高い除菌率を認めた。
・有害事象は3剤併用療法と差を認めなかった。
この論文の結果で特に注目したいのが、クラリスロマイシン耐性がある場合は、2剤併用療法のほうが除菌率が高いという点です。
これからは薬剤耐性菌の存在を確認するためにもピロリ菌の培養同定とともに、クラリスロマイシンに対する薬剤感受性試験を行うことの重要性が高まってくるかもしれません。
今後の症例の積み重ねによる検討が必要ですが、ひょっとしたら現在保険適応となっている一次除菌療法の3剤併用療法から、今後は2剤併用療法が主流となる可能性を秘めていると思います。今後の検討に期待したいです。
ピロリ菌がいるかどうか気になる方や除菌について不安な方は、ピロリ菌除菌を積極的に行っている当院までぜひお任せください。